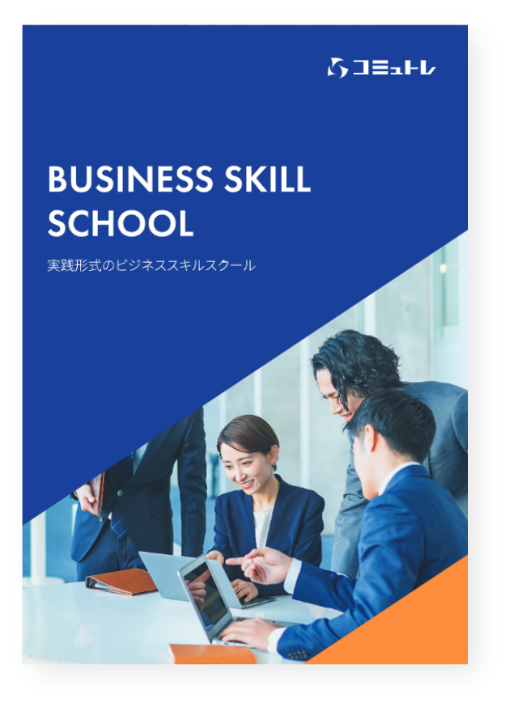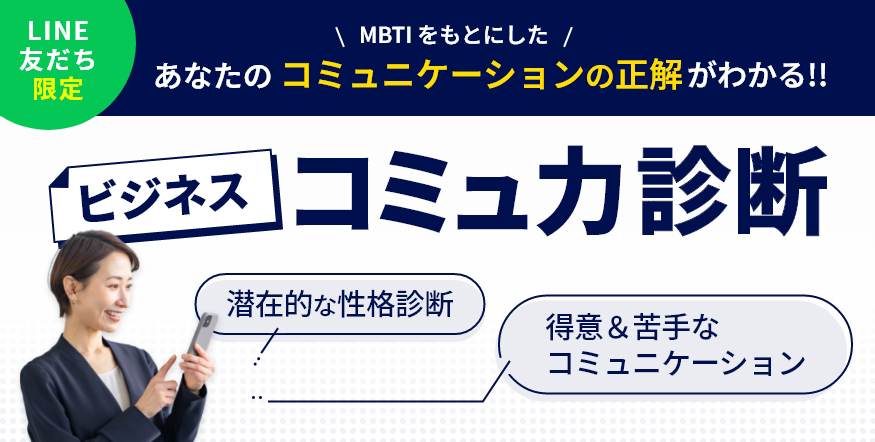「一生懸命考えたつもりなのに、話すと結局いつもツッコまれてしまうんです(泣)だから意見を言うときもつい緊張しちゃって…」というご相談は、ほぼ毎日いただきます。
一方で、「なんでそんな的確な質問や鋭い意見が出るんですか?」と、聞き手もうなる発言をする人もいますよね。
こういう同僚に出会うたびに、私はさすがだなと尊敬する反面、めちゃくちゃ悔しかったんです。
(特に相手が自分より年下の場合は!)
でも、追いつけない…。
そういう経験を繰り返すうちに、「自分は人よりも頭が悪いんじゃないか」と謎のコンプレックスを抱くようになりました。
しかし、本業であるコミュニケーションの勉強を深め、さまざまな受講生の成果報告を聞くうちに、「なーんだ、説得力がある人ってここを押さえていたんだ!」というポイントがわかってきました。
そこで今回は説得力のある人がやっている話し方の工夫や、説得力のある人の特徴をお伝えします。ぜひ、自分の意見に自信がもてない方にこそ読んでもらいたいなと。
説得力の具体的な上げ方は、また別の記事でお伝えしますね。
前提として、「説得力=話し方+話す中身」としたときに、今回の記事では「話す中身」に焦点を当てていきます。話し方については別の記事で取り上げます。
目次
ビジネスで説得力のある話し方が重要な理由
ビジネスで説得力のある話し方が重要な理由は、他人の考えや心を動かさない限り、成果がでないためです。
欲しいとも思わない商品を購入したり、いいと思わない企画を通したりはしませんよね?
商談やプレゼンでは、相手に「それはいい商品だ」「だからうちに必要なのか」と思わせなければいけません。部下への指導でも同様です。「なるほど」と思わせなければ、素直に聞き入れてくれないでしょう。
そのため、営業やマネジメント職だけでなくあらゆる職業の方にとって、説得力のある話し方が重要です。
説得力のある話し方を実現する5つのポイント
本章では、説得力のある話し方を実現する、5つのポイントを紹介します。
- 事実に基づいている
- 多角的視点で語っている
- 相手が理解できる言葉を使用する
- 時にはデメリット面をきちんと伝える
- 非言語コミュニケーションに長けている
商談やプレゼン、部下への指導で悩んだ経験をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
1. 事実に基づいている
主張の説得力を高める最重要な要素は、ズバリ事実です。
主張の構成要素は、大きく「結論(〜すべきである、など)」と「根拠」に分かれます。
私たちが何かの主張を聴いて「なるほど」と感じるとき、実は結論そのものに納得しているわけではありません。そうではなく、その結論に至った筋道、つまり根拠になっている「事実」に鋭さを感じるのです。
例を挙げましょう。
コミュトレスタッフはよく「顧客満足度を上げるための作戦会議」を開きます。
そこで、以下のような発言をしたらどうでしょうか。
「学習意欲を高めるためには、受講生に成果報告してもらう場を定期的に設けるべきだと思います。なぜならば、具体的な実践事例を知ることで、自分に生かすためのヒントを得られると思うからです。」
下線部は一見もっともらしく表現されていますが、事実ではなくすべてその人の推測です。そのため、結論が正しいかどうかの判断ができません。つまり、言っても言わなくても大差ない。厳しいことを言えば、情報としての価値はゼロです。
これでは「ほんとに?それはあなたの思い込みじゃないの?」と言われてもグウの音も出ません。
では、同じ結論を、このように根拠を付けて話したらいかがでしょうか?
「学習意欲を高めるためには、受講生に成果報告してもらう場を定期的に設けるべきだと思います。なぜならば、成長を実感している受講生A氏にその理由を聞いたところ、他の人の活用事例を積極的に聞くことでヒントを得られた、と話していたからです。なので、今回はその声を取り入れてみました。」
実行したら本当に結論通りになるかどうかは別として、後者のほうが「事実に基づいて考えている」と感じませんでしたか。
「あー、確かにそういう事実ってあるよね。」「へえー、そんな事実があったんだ。知らなかった!」と、心の声が聞こえてくるようですよね。
これがズバリ、「なんか説得力ある」という印象の正体です!!そのため、説得力のある人の話し方は、事実をもとにして話している特徴がみられます。
説得力アップに向けて「論理的思考」を強化したい方はこちらもどうぞ!
2. 多角的視点で語っている
説得力のある人がやっているもう一つの工夫は、多角的視点で語ること。
先ほどの、「事実に基づいて発言する手法」の最大の弱点って、なんだかわかりますか。
そう、偏った事実を取り上げてしまうことなんです。
先に出た「学習意欲を上げる施策」の例をもう一度見てみましょう。
「学習意欲を高めるためには、受講生に成果報告してもらう場を定期的に設けるべきだと思います。なぜならば、成長を実感している受講生A氏にその理由を聞いたところ、他の人の活用事例を積極的に聞くことでヒントを得られた、と話していたからです。なので、今回はその声を取り入れてみました。」
この主張に反論すると、以下のようになります。
・そもそも、その受講生が「勉強に自信がある(特別な)人」だったのでは?・そもそも、その受講生が聞いた活用事例が、たまたまその人の業種と似ていたからじゃないの?・そもそも、その受講生同士がたまたま仲良かったから、素直にやってみようと思えただけじゃないの?
今回の例のように事実が1つだけだと、以下のツッコミによって、いとも簡単に論破されてしまいます。
「その事実がそもそも特殊なケースだとしたら、再現性が低いのでは?」
「他の事実の方が、実はもっと影響が大きいのでは?」
一方で、以下のように複数の観点から事実を並べたらどうでしょうか。
「学習意欲を高めるためには、受講生に成果報告してもらう場を定期的に設けるべきだと思います。なぜならば、1.【受講生の経験という観点】
成長を実感している受講生A氏にその理由を聞いたところ、他の人の活用事例を積極的に聞くことでヒントを得られた、と話していたからです。2.【自分自身の経験という観点】
私自身も朝礼スピーチで、仕事での成功経験を同僚が話しているのを聞くと、自分も頑張ろうと思えてきます。3.【人間の習性という観点】
しかも、人間には「自分で話した言葉が自分自身に作用する」習性があります。実際、友人に悩みを打ち明けているうちにだんだん頭が整理されてきて、解決方法が思い浮かんだりしますよね。なので、自分の成功経験を話すことでより気づきを得られるかと思います。
このように、2つ以上の異なる観点から事実を並べられると、「特殊な事例では?」「他の要因を見落としているのでは?」というツッコミに強くなります。
これが、多角的な視点で話すこと。
逆を言えば、2つ3つの観点から事実を並べてしまえば、それだけでどのような結論であれ説得力があるように聞こえてきます。つまり、説得力の有無は、センスや頭の回転の速さよりも、むしろ情報量の差によって決まっているのです。
説得力を上げたいなら、論理的思考よりも『顧客視点』を徹底しよう☒ 会議に自信をもって参加するには準備が大事!
【保存版】会議・打ち合わせに自信をもって参加する3つの心得☒ 説明力アップを目指したい方はこちらも必見!
説明上手は使っている!難しい話を面白い話に変えるメタファーの使い方
説明力を高めるコツを5つ解説する【効果保証&講師監修】
説明力とは?説明力が高い人の特徴も一挙解説!
説明力をこっそり鍛える自主トレーニング方法【講師も実践中】
3.相手が理解できる言葉を使用する
相手が理解できる言葉の使用も、説得力のある話し方を実現するためには大切です。相手にわからない言葉を用いると、聞く気を削いでしまいます。一生懸命説明しているのにまったく聞いてもらえないのは悲しいですよね。
説得したい場合は、相手の理解度に合わせた言葉選びを行いましょう。相手の理解度がわからない場合は、誰もがわかる簡単な言葉に変換して話すのがおすすめです。
「中学生でもわかる説明」を目指すとよいでしょう。
専門用語を専門家ではない方に多用すると、「説明する気がないな」「マウントをとりたいだけか?」と思われ、もう話を聞いてもらえません。なるべく使用せずに話しを構成してみてください。
4.時にはデメリット面をきちんと伝える
説得力のある話し方を実現するためには、時にはデメリット面をきちんと伝えることも重要です。
「デメリットを伝えるのは説得力が落ちるから嫌だ」と考えている方も多いでしょう。しかし、商談やプレゼンでメリットばかりを説明する方が、説得力は落ちてしまいます。
たとえば、服屋で試着する度に「お似合いですね」と褒められると、どう思うでしょうか?「こいつ嘘くさいな…」と思いますよね?
デメリットに触れずに説明すると、聞き手の信用を失ってしまいます。説得力を高めるには、デメリットをきちんと伝えましょう。
特に、聞き手が「こういうデメリットがあるんじゃないか?」と疑問を抱いている時に伝えられると、高い信頼が得られます。聞き手が抱きそうな疑問を事前に想定しておくとよいでしょう。
5.非言語コミュニケーションに長けている
非言語コミュニケーションに長けていることも、説得力のある話し方の実現には大切です。非言語コミュニケーションとは、ジェスチャーや身だしなみ、表情・声のトーンのことです。
意識するだけでも、以下の3つの効果が得られます。
- 信頼関係を構築しやすくする(前のめりで話を聞くなど)
- 相手への理解を深められる(表情を見て感情や意思を察するなど)
- 話の内容を補完できる(声のトーンで大事な部分を強調するなど)
同じ内容でも、非言語コミュニケーションのうまさで説得力は大きく異なります。
非言語コミュニケーションを伸ばすには、うまい人の真似がおすすめです。身近に説得力の高い方がいれば、ぜひ真似をしてみてください。
説得力のある話し方ができる人の3つの特徴
本章では、説得力のある話し方ができる人に共通した、3つの特徴を紹介します。
- 人前で自信を持って話せている
- 本質的な内容に目を向けている
- マナーがきちんと身に付いている
説得力のなさに悩む方は、ぜひ今一度見直してみてください。
人前で自信を持って話せている
説得力のある話し方ができる人の特徴として、人前で自信を持って話せている点が挙げられます。
メラビアンの法則では、相手に影響を与える割合は、「言語情報が7%」「聴覚情報が38%」「視覚情報が55%」です。すなわち、人は内容よりも声のトーンや視覚情報に大きな影響を受けます。
実際に商談を受ける立場になったと考えて、想像してみてください。オドオドしながら小さな声で話す人と、大きな声で堂々と話す人とでは、説得力に大きな違いがありますよね?
「内容は正しいのに納得してもらえない」と悩む方は、堂々と話すだけでも解決する可能性があります。ぜひ、試してみてください。
本質的な内容に目を向けている
本質的な内容に目を向けていることも、説得力のある人の特徴です。説得力のある人は相手の抱える課題・問題をより深く考え、根本から解決するにはどうしたらよいかを述べます。
そのため、聞き手が「そうか、そのせいで今までうまくいかなかったのか」と思うほど、納得する話ができます。
反対に、説得力のない人は、表面的な要望や欲求にとらわれがちです。「言われた課題を解決できた」「いいプレゼンができた」と思っていても、聞き手にまったく響かなかった経験はありませんか?
相手の要望に素直に応じるのではなく、「なぜそんな要望を出すに至ったのか」を考える癖をつけておきましょう。
マナーがきちんと身に付いている
説得力のある人の特徴として、マナーがきちんと身についていることも挙げられます。服装やマナーは、相手の印象に大きな影響をもたらすためです。
たとえば、ラフな服装でマナーも悪い人から「いい話があるんですよ」と言われても、信じられませんよね?身だしなみやマナーが悪くなるほど、相手からの信頼も下がります。
重要なビジネスマナーは、以下の4点です。社会人として、常に心がけておきましょう。
- 時間を守る
- 報連相はきちんとする
- あいさつは元気よく
- 整理整頓をする
説得力のある話し方を実現する具体的な施策とは?
本章では、説得力のある話し方を実現する、具体的な施策を紹介します。
- コミュニケーションの本で勉強する
- コミュニケーションのプロに相談する
どうすれば説得力のある話し方ができるのか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
コミュニケーションの本で勉強する
説得力のある話し方の実現には、コミュニケーションの本での勉強が大切です。以下の3冊の本がわかりやすく、おすすめです。
- 話せる、伝わる、結果が出る!コミュトレ 10万人のデータから導き出されたビジネス・コミュニケーションスキル/著者:野田雄彦氏
- 頭のいい人が話す前に考えていること/著者:安達裕哉氏
- 人は話し方が9割/著者:永松茂久氏
説得力を高めるために努力してきた方の中には、「たくさんの本を読んでみたが身につかない…」と悩む方も多いでしょう。
大切なのは、「納得した本の納得した部分を何度も読み、実践を繰り返す」ことです。ぜひ取り組んでみてください。
コミュニケーションのプロに相談する
コミュニケーションのプロへの相談も、説得力のある話し方の実現に向けた、具体的な施策です。
説得力のある話し方を身につけるには、多くの実戦経験とフィードバックが必要です。しかし、実際の商談やプレゼンの場を練習台にしたり、相手からフィードバックを受けたりはできません。
そのため、実践形式で学べるコミュニケーションのプロへの相談がおすすめです。
「コミュトレ」では、Web講義に加えて実践形式のトレーニングを行っており、説得力のある話し方を身につけられます。
また、自身の話に説得力がない原因がどこにあるのか、分析できる無料診断も行っています。ぜひ、下記から申し込んでみてください。
まとめ:説得力のある人の話し方を真似よう
今回の記事を通して1番お伝えしたかったのは、「説得力のある人は、必ずしも特別なセンスや才能をもっているわけではない」ことです。
「身だしなみがきっちりしている」「自信を持って堂々と話している」これらは誰にでもできることですよね?
つまり、決して一部の人が先天的にもつ頭の良し悪しやセンスの問題ではないので、決してあきらめてほしくないと思います。
また、話の中身だけに限定すれば、説得力とはズバリ「多角的な観点からの事実によって、結論が導かれているか」どうかにかかっています。
こちらもあわせてご覧ください!
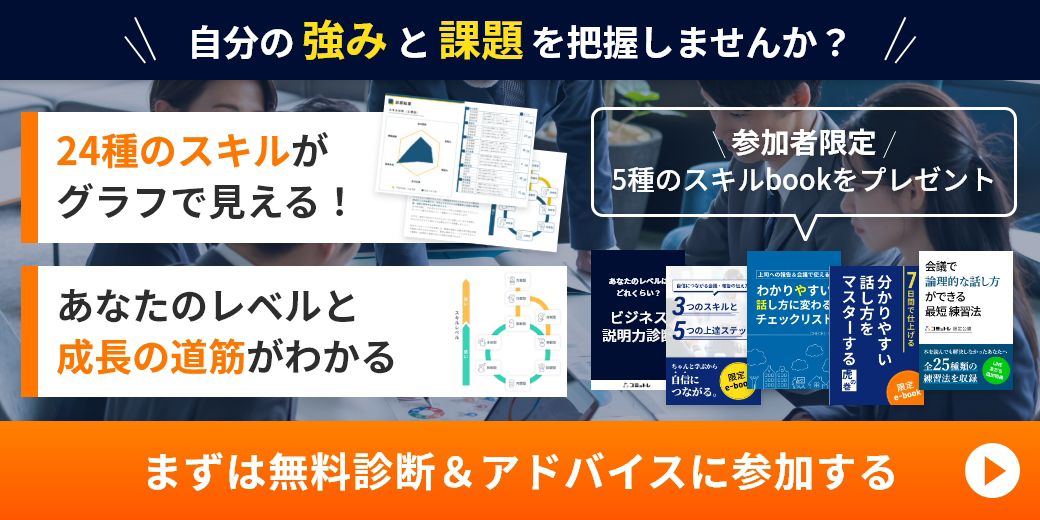
5秒で簡単 コミュトレの資料をダウンロードする