「ロジカルに考えよう」
「ロジカルに話さなければ」
誰もが、社会人になってから1度は意識したことがあるでしょう。
しかし、そもそも「ロジカルである」がなにを指すのか、わかっている方はあまりいません。
その結果、「よくわからないけど、なんだか難しそう…」と構えてしまっている人も多いでしょう。
本記事では、ロジカルシンキングのトレーニング方法を紹介するとともに、ロジカルシンキング自体も掘り下げて解説します。
私たち人間は正体が分からないものに出会うと、リスク回避のための防衛本能が働き、過剰に苦手意識をもってしまいがちです。
ぜひこの記事を通じて、「ロジカルである」ことの正体を知り、「なんだ、意外に難しくない!」と感じられるようになりましょう!
また、「コミュトレ」の無料セミナーでは、コミュニケーションの強みと課題を把握できます。
自身が「ロジカルに考えられない」正体も具体的にわかるため、少しでも興味がある方は、ぜひ下記からお申し込みください。
📚「ロジカルに考えるのが苦手…」という方は、こちらもどうぞ!
目次
【 日常からできる】ロジカルシンキング7つの鍛え方
次に、日常からロジカルシンキングを鍛える方法として以下の7つを紹介します。
- フレームワークに沿って話をする
- インプットとアウトプットを大切にする
- 双方が話すことを意識する
- 仮説を立ててから説明する
- 話の冒頭で主張を簡潔に説明する
- 本で勉強する
- 研修やセミナー、ディベートに参加する
それぞれの鍛え方を詳しく解説するので参考にしてください。
フレームワークに沿って話をする
ロジカルシンキングを鍛える方法として、フレームワークに沿った会話が挙げられます。
会話のフレームワークの中で、基本的なものが「ピラミッド構造」です。
ピラミッド構造とは、物事の結論をピラミッドの頂点に置き、その下に根拠を付け加えていくことで情報を整理するフレームワークを指します。
ピラミッド構造に沿って話すことで結論や根拠が整理しやすくなり、簡潔に話せます。
他にも、「ミーシー」や「ロジックツリー」、「演繹法・帰納法」などさまざまなフレームワークが存在するので覚えておきましょう。
フレームワークに沿った話を癖づければ、自然とロジカルシンキングは鍛えられます。
ミーシーなどのフレームワークは、後ほど詳しく解説します。
インプットとアウトプットを大切にする
インプットとアウトプットも、ロジカルシンキングを鍛えるには重要です。
インプットとは情報の吸収を、アウトプットとは集めた情報の披露を指します。
繰り返すと頭の中の生きた知識が増え、ロジカルに考えるための材料が増えるため、ロジカルシンキングが身につくでしょう。
反対に、インプットもアウトプットもしなければ、話法を磨いても考える材料がないためロジカルには話せません。
インターネットやSNS・同僚との会話から、テーマに合わせて情報を収集し、折を見て誰かに披露して生きた知識にしてみてください。
双方が話すことを意識する
双方が話すことへの意識も、ロジカルシンキングを鍛える際には求められます。
一方的に話すだけでは、相手の意見を分析する力や、自分を客観視する力が身につかないためです。
発言の意図を汲めない人や自分の間違いに気づけない人を見て、ロジカルシンキングができていると思う人はいません。
日常から双方向の会話を意識すると、自分と相手の発言に対して考える機会が増え、自然とロジカルシンキングのトレーニングができます。
相手が話し始めるのを待つようにしてみましょう。
仮説を立ててから説明する
ロジカルシンキングを鍛える方法として、仮説を立ててからの説明が挙げられます。ロジカルシンキングの仮説とは、現在起きている事象に対する解決方法を考えることです。
物事を素早く、効率的に解決するためには、漠然と情報を集めることはおすすめできません。
今ある情報から課題に対する仮説を立て、その仮説を検証するステップを繰り返すことで効率的かつ本質をとらえた課題解決ができます。
日常生活から仮説を立てることを意識すると、ロジカルシンキングが鍛えられるでしょう。
話の冒頭で主張を簡潔に説明する
ロジカルシンキングの鍛え方として、話の冒頭で主張を簡潔に説明する方法も挙げられます。
特に、上司への報告やプレゼンなどの場面では、冒頭で主張を伝えることは非常に重要です。
会話のフレームワークの基本の「ピラミッド構造」を意識して、主張の後に根拠や事例を伝えると情報がまとまって伝わりやすくなります。
特に「結局何が言いたいのかわからない」と言われたことのある人は、話の主張や結論を冒頭で伝えることを意識しましょう。
本で勉強する
本での勉強も、日常的にできるロジカルシンキングを鍛えるおすすめの方法です。
独学で練習しても、新たな考え方やテクニックは増えません。本を読み、コミュニケーションのプロの考え方やテクニックを、自分に追加しましょう。
ロジカルシンキングを学ぶためのおすすめの本は、以下の3冊です。
- 話せる、伝わる、結果が出る!コミュトレ:10万人のデータから導き出されたビジネス・コミュニケーションスキル/著者:野田雄彦氏
- ロジカル・プレゼンテーション/著者:高田貴久氏
- 頭がいい人の思考術 日本一やさしいロジカルシンキング/著者:伊庭正康氏
研修やセミナー、ディベートに参加する
ロジカルシンキングを鍛える方法として、研修やセミナー、ディベートへの参加も挙げられます。
研修やセミナー・ディベートでは、ロジカルシンキングを鍛えるための基本的な考え方や、会話のフレームワークなどの専門的な内容を学べます。
研修やセミナーが集団で受講する形式であれば、学習した内容を実際に他の生徒と実践できることがメリットです。
また、学んだ内容はアウトプットすると定着しやすくなります。
積極的な研修・セミナー、ディベートへの参加によって自然とアウトプットの機会が増え、深い学びを得られます。
自分の思考の癖を指摘してもらえるため、本格的にロジカルシンキングを鍛えたい方は積極的な参加がおすすめです。
ロジカルシンキングが鍛えられる無料診断を詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください!
【例題あり】 ロジカルシンキングとは?|主張と根拠をつなげて考えること
鍛え方がわかっても、「ロジカルシンキング」とはそもそもなにを指すのかがわからなければ、効率のよいトレーニングはできません。
「ロジカルシンキング」とは、「主張」と「根拠」のつながりです。
私たちは、これらのつながりを聞いて違和感がないとき、「ロジカルな話だ」と感じます。
反対に、主張と根拠のつながりに無理がある場合は、「ロジックが飛躍している」と感じてしまいます。
本章では、ロジカルシンキングに重要な「主張」と「根拠」を、NG例とOK例を交えながら詳しく解説します。
- 主張とは「問い」に対応した自分なりの考え
- 根拠は主張の正しさを裏付ける証拠
日常的によく使われている言葉ですが、ロジカルシンキングを正しく実行するには意味を正確に知っておくことが重要です。
認識が曖昧な方は、ぜひ最後までお読みください。
主張とは、「問い」に対応した自分なりの考え
「主張」とは、ある「問い」に対する自分なりの「回答」です。
ここでいう回答とは、自分なりの考えや推論を指します。
私たちが自分の考えを伝えるとき、意識しているか否かに関わらず、その考えは必ずなんらかの問いに対する回答になっています。
反対に、問いがなければ、その問いに対応する主張も生まれません。
たとえば、「今日の昼はラーメンにしよう」この主張は、「今日の昼は何を食べようかな」との問いから生まれたものです。
決して「今日はなんの予定があるんだっけ」のような、まったく脈絡のない問いから生まれた考えではありません。
したがって、ロジカルシンキングを行うときは、「問い」を正しく理解するのが大前提になります。
そのうえで、問いに対応する回答を考えることで、自分の主張が生まれます。
つまり、問いが誤っていると主張と根拠がつながっていても、なんの話なのかわからず聴き手を混乱させてしまいます。
以下、NG例とOK例を比較して詳しくみていきましょう。
主張と問いが対応していないNG例
問い:「新卒採用で学生を選ぶとき、どのような能力を重視するとよいですか?」主張:「私は、『学生時代にどんな失敗をしたのか』を聞くべきだと思います。その理由は、失敗経験を聞くことによって、失敗に対するストレス耐性を見極めたり、うちの会社で成長していけるかを予測したりできるからです」
この例では、「重視すべき能力はなにか」を問われているにも関わらず、「面接での質問内容」を回答してしまっています。
回答の中には理由も含まれているものの、問いと主張がかみ合っていないため、「なぜ面接での質問内容を話しているのだろう」と聴き手は混乱してしまいます。
主張と問いが対応しているOK例
問い:「新卒採用で学生を選ぶとき、どのような能力を重視するとよいですか?」主張:「私は、コミュニケーション能力を重視すべきだと考えます。なぜなら、意思疎通が正しくできるので、安心して仕事を任せられるからです」
この例では、「重視すべき能力はなにか」の問いと、「コミュニケーション能力を重視すべきだ」との主張がうまくかみ合っています。
そのため、聴き手はスムーズに理解できます。
このように、ロジカルシンキングを行うには、まず「問いと主張を対応させること」が大切です。
「ちゃんと伝わるかな?」と不安になった際は、自分の主張がどのような問いに対する回答なのかを、整理してみてください。
📚 仕事で意見を求められることが増えてきた方は、以下の記事もチェックして自己主張スキルを高めてみませんか?
根拠は、主張の正しさを裏付ける証拠
続いて、「根拠」も見ていきましょう。
「根拠」とは、主張の正しさを裏付ける証拠です。
主張は、あくまでも自分の考えや推論であって、客観的な事実ではありません。
したがって、主張の妥当性を証明するためには、根拠を使った裏付けが不可欠です。
聴き手が根拠を聞いて「たしかにそうだな」と思えば、ロジカルで筋が通っていることになります。一方で「ん?その根拠は関係ないのでは?」と思えば、話が飛躍していることになります。
では、「根拠」に該当する情報として、一体何を伝えればよいのでしょうか。
情報には、「経験」「ルール」「データ」などさまざまな種類がありますが、これらはすべて根拠として用いられます。
ただし、そのどれであっても、主張の正しさを裏付けるものでなければなりません。
したがって、自分の考えが論理的かどうかを確かめるには、根拠が主張の正しさを裏付けているかの見直しが大切です。
主張と根拠をそれぞれ見直して違和感がなければ、論理的な意見を構築できています。
以下、NG事例とOK事例を比較して詳しく見ていきましょう。
根拠が主張の正しさの裏付けになっていないNG例
問い:人生を100歳までと考えたら、今後どのようなビジネススキルが重要になるか?主張:コミュニケーションスキルが最も重要になるだろう(推論)根拠:日本経済団体連合会の資料によると、新卒採用で重視される能力の第1位はコミュニケーション能力だから(データ)
NG例では、根拠として「新卒採用で重視される能力のデータ」を挙げています。
しかし、そのデータだと、人生の若い頃に必要な能力にしか言及できていません。
今回の主張の、「人生を100歳と考えたとき、今後重要な能力はコミュニケーション能力である」の、正しさを裏付けているとはいえません。
したがって、論理が飛躍してしまっています。
根拠が主張の正しさの裏付けになっているOK例
問い:人生を100歳までと考えたら、今後どのようなビジネススキルが重要になるか?主張:コミュニケーションスキルが最も重要になるだろう(推論)根拠:自社では、定年を迎えた人の再雇用により、70代の社員と20代の若手社員が一緒に働いている。その中で、先日、お互いの考え方を理解し合えず関係が悪化した結果、若手社員が離職してしまったから(経験)
OK例では、主張の正しさを裏付ける根拠として、「自社の経験」を挙げています。
世代が異なる社員間でコミュニケーションをスムーズにとれていれば、20代の社員は離職しなくて済んだかもしれません。
そのため、今回の主張の「人生100年時代では、コミュニケーション能力が重要」の裏付けとなっています。
これが、主張の正しさが裏付けされた、論理的な思考です。
ロジカルシンキングを行うときは、「根拠が主張の正しさを裏付けているかどうか」に、注意を払いましょう。
ロジカルシンキングの習得に欠かせない4つのフレームワーク
本章では、ロジカルシンキングの習得に欠かせない、4つのフレームワークを紹介します。
- ミーシー
- ロジックツリー
- 演繹法
- 帰納法
それぞれ使い方も紹介するので、ぜひ試してみてください。
ミーシー
ロジカルシンキングの習得に欠かせないフレームワークとして、ミーシーが挙げられます。
ミーシーとはMECEと書き、「漏れなく、ダブりなく」を意味する、「Mutually Exclusive Collectively Exhaustive」の頭文字からなる言葉です。
物事に対する理解度を高めることや、新たな視点から考えることに役立ちます。
たとえば、自社商品と他社商品を機能・価格・デザインなどで分類すると、競合が少ない部分や人気に直結する部分が見えてくるでしょう。
MECEには、全体から詳細に向けて考えるトップダウンアプローチと、詳細を集めてから全体像を描くボトムアップアプローチがあります。
全体像がわかるか不明瞭かで、使い分けてください。
ロジックツリー
ロジックツリーも、ロジカルシンキング習得に役立つフレームワークです。
問題や原因を可視化して分解するため、複雑な事柄もとらえやすく、解決法を容易に導き出せるでしょう。
ロジックツリーは考えたい問題を頂点に置き、大きな原因・要素に分解して、それをさらに小さな原因・要素に分解して作成します。
たとえば、「貯蓄ができない」問題を頂点に置くと、「無駄遣いが多い」「収入が少ない」「管理できていない」の3つの原因に分解できます。
それら3つの原因をさらに細かく分析して、それぞれの理由を考えると、なぜ貯蓄ができていないのかがわかるでしょう。
要素の分解・原因追及・問題解決の際に、ロジックツリーを使ってみてください。
演繹法
ロジカルシンキング習得に欠かせないフレームワークとして、演繹法(えんえきほう)も挙げられます。
戦略策定や製品開発など悩ましい場面で、論理的に最適な結論を導き出せるためです。
演繹法は、疑いようのない事実を基に推論して結論を導く方法であり、以下のように用いられます。
【演繹法の例】事実:近年はアジア市場が成長している事実:類似商品はアジアでも使用されている結論:アジア市場での需要が高まることが見込まれる
漠然とした状況でなにをすればよいかわからない際に使うと、結論が自然と出て、今後の対応も見えてくるでしょう。
また、演繹法は後述する帰納法も同時に活用すると、正確性が向上します。
帰納法
帰納法(きのうほう)も、ロジカルシンキング習得に欠かせないフレームワークです。
帰納法では、複数の事例・データから共通点を見つけ、そこから結論を導き出します。具体的には、以下のように用います。
【帰納法の例】事例:競合A社はECサイトでアジア進出に成功した事例:競合B社はECサイトでアジア進出に成功した事例:競合C社は店頭販売でアジア進出に失敗した共通点:ECサイトならアジア進出に成功する結論:自社もECサイトを活用してアジア進出をする
帰納法や演繹法で気をつけるべき点は、出された結論はあくまで推論であり、必ずしも正しいわけではないことです。
ロジカルシンキングには他人の意見に耳を貸すことも重要と、覚えておきましょう。
ロジカルシンキングを鍛える3つのメリット
次に、ロジカルシンキングを鍛えるメリットを3つ紹介します。
- 課題を発見する力・解決する力が身につく
- 提案力の向上
- コミュニケーション力の向上
それぞれのメリットを詳しく解説します。
課題を発見する力・解決する力が身につく
ロジカルシンキングを鍛えるメリットとして、課題を発見する力や解決する力が身につくことが挙げられます。
課題を発見する力が高まると、課題に対する情報の漏れや重複を防げるため、構造的に整理できます。
情報が整理されると因果関係も正しく把握でき、より効率的かつ本質をとらえて、課題解決に取り組めるでしょう。
情報の深掘りにも役立つため、今後同様の課題が発生しづらくなるメリットもあります。
提案力の向上
ロジカルシンキングを鍛えるメリットとして、課題に対する提案力の向上も挙げられます。
ロジカルシンキングによって、主張に対する根拠を発見・構造的に整理しやすくなると、主張の納得感が高まるためです。
たとえば、プレゼンで自社の商品がどのような課題をどう解決できるのか、根拠を持って説明できれば受注率は格段に上がるでしょう。
相手が納得できる根拠が多いほど主張は通りやすくなるため、ロジカルシンキングには提案力を向上させるメリットがあります。
コミュニケーション力の向上
ロジカルシンキングを鍛えるメリットとして、コミュニケーション力の向上も挙げられます。
ロジカルシンキングによって情報を整理しやすくなると、主に以下の理由からコミュニケーションのすれ違いを防げるためです。
・報告すべき事項を優先的に報告できる
・論点のズレが少なくなる
・「事実」と「意見」の違いが最小限になる
たとえば、上司への報告やメール文面作成の際には、相手の把握したい情報を最優先で伝えられます。コミュニケーションは日常で頻繁に行われるため、ロジカルシンキングを鍛えることで、多くのミスを減らすことができるでしょう。
ロジカルシンキングを鍛える際のポイント
ロジカルシンキングを鍛えると、さまざまなビジネスシーンで違いを感じられるでしょう。
そのためにも、日常からできるロジカルシンキングのトレーニングを、ぜひ実施してみてください。また、その際には、以下のポイントを意識すると効率的に成長できます。
- 現状を言語化する癖をつける
- 自分の思考の癖に気づく
- 主張と根拠をセットにする
言語化する癖をつけるには、「どのような課題を解決する話なのか」「なぜこのトレーニングを行うのか」を、常に自身に問いかけるのがおすすめです。
自分の思考の癖に気づくには、意識的に自分の考えを批判的に見る、「クリティカル・シンキング(批判的思考)」がおすすめです。
ロジカルシンキングのトレーニングにおすすめのゲーム5選
本章では、ロジカルシンキングのトレーニングにおすすめのゲームを5つ紹介します。
- ビブリオバトル
- 人狼ゲーム
- マーダーミステリー
- コリドール
- ナンバーワン・ベーカリー
楽しみながらロジカルシンキングが鍛えられるので、参考にしてください。
ビブリオバトル
ビブリオバトルは、本を使ったディスカッションです。
各参加者は自分が気に入った本を1冊ずつ持ち寄り、設定された時間でその本の魅力を紹介します。
その後、全員で各本のディスカッションを行い、最も読みたくなった本を投票で選びます。
ビブリオバトルにより、「自分の考えを論理的に伝達する」「明瞭かつ理論的に会話を進める」「本のメッセージを理解し他人に分かりやすく伝える」など、ロジカルシンキングのスキルを実際の状況で磨けるでしょう。
人狼ゲーム
人狼ゲームは、数人から10人程度のグループで行われる推理型ゲームです。
参加者は「村人」や「騎士」などの役割が割り当てられ、その中には「人狼」が混じっています。
ゲームが開始すると、夜ごとに人狼により参加者が1人ずつ攻撃されます。
参加者はディスカッションを通じて人狼を見つけ出し、村が全滅するのを防ぐことが目的です。
人狼ゲームを通して、「自分の思考を他者に明確に伝える」「起こった出来事を論理的に分析し、人狼の正体を探り出す」「誤った前提に基づかない論理的な推理をする」など、ロジカルシンキングの練習ができます。
また、ロジカルシンキングだけでなくコミュニケーションスキルや、話の構築方法も学べるでしょう。
マーダーミステリー
マーダーミステリーは、参加者が物語のキャラクターとなり、ロールプレイを行いながら物語の謎を解き明かすTRPGです。
マーダーミステリーは、人狼ゲームよりも大規模な参加者を対象にしているのが特徴です。
また、通話アプリや専用のサイトを使うことでオンラインでも開催できます。
真相を明らかにするためには、嘘をついたり嘘を見破ったりしなければいけません。
その過程で、他者を自分の主張に納得させるための、ロジカルシンキングを学ぶ機会が得られます。
コリドール
コリドールは、2〜4人のプレイヤーがそれぞれのコマと壁を操作し、ゴールラインへの到達を目指すボードゲームです。
起源はフランスで、約20分の短い時間で遊べる利便性があります。
壁の設置方法やコマの移動方法には特定のルールがあり、コリドールで勝つためにはロジカルシンキングが不可欠です。
ナンバーワン・ベーカリー
ナンバーワン・ベーカリーは、起業体験型のボードゲームです。
パン屋を成功させる目的の下、プレイヤーは経営戦略とマーケティングの知識を利用して、ゲームを進めていきます。
このゲームではロジカルシンキングを磨けるだけでなく、売上・費用・利益・キャッシュフローなど、ビジネス運営に不可欠な概念への理解も深められるでしょう。
そのためナンバーワン・ベーカリーは、企業の研修や商工会議所のセミナー、高校や塾などの教育機関で活用されています。
ロジカルシンキングトレーニングに使える無料アプリ
最後に、ロジカルシンキングのトレーニングができる、無料のアプリを2つ紹介します。
- DNB
- Xmind
2つのアプリを詳しく解説します。
① DNB</h3>
DNBは、「15分でIQがアップする」をテーマに作られた脳トレアプリです。
メンタリストDaiGoが制作・監修しており、ついやってしまうような簡単でおもしろい脳トレが用意されています。
また、DNBは目的に合わせて難易度や問題数を変えられる点も特徴です。
「脳トレを楽しみたい」「ロジカルシンキングを本格的に鍛えたい」など、さまざまなニーズに沿った問題が用意されています。
スキマ時間で手軽に体験できるので、手軽にロジカルシンキングを鍛えたい方におすすめです。
②Xmind
Xmindは、香港で開発されたマッピングツールです。
Xmindでは、組織関係図やロジックチャートをはじめとした、さまざまな形式の図表でアイデアを整理できます。
スプレッドシートの機能も兼ね備えているため、データ管理や共有も簡単に行えます。
自分や他の人の思考を視覚化すると情報整理がしやすくなるため、会議だけでなく移動時間などに書き込んでみるのもおすすめです。
まとめ|最短で ロジカルシンキングを鍛えるにはセミナーで学ぼう
今回は、日常からできるロジカルシンキングの鍛え方を解説しました。
ロジカルシンキングとは、主張と根拠をつなげて考えることです。
主張とは「問い」に対応した自分なりの考えであり、
根拠とは主張の正しさを裏付ける証拠です。
これらをつなげるためにも、フレームワークの活用や仮説を立てて話すことを、重視してみてください。
しかし、「これまで努力してきたがいまだできていない」とおっしゃる方も多いでしょう。その場合は、自身にどのようなスキルが不足していてできないのか、確認してみるのがおすすめです。
ビジネススキルスクールの「コミュトレ」では、コミュニケーション能力の強みと弱みが把握できる、無料セミナーを行っています。
ロジカルに考えられない理由がわかった状態でのトレーニングは、今までのトレーニングよりも格段に効率がよく、最短でロジカルな思考を身につけられるでしょう。
📚 ロジカルシンキングが求められる代表的な場面である『会議』に、自信をもって臨むには?


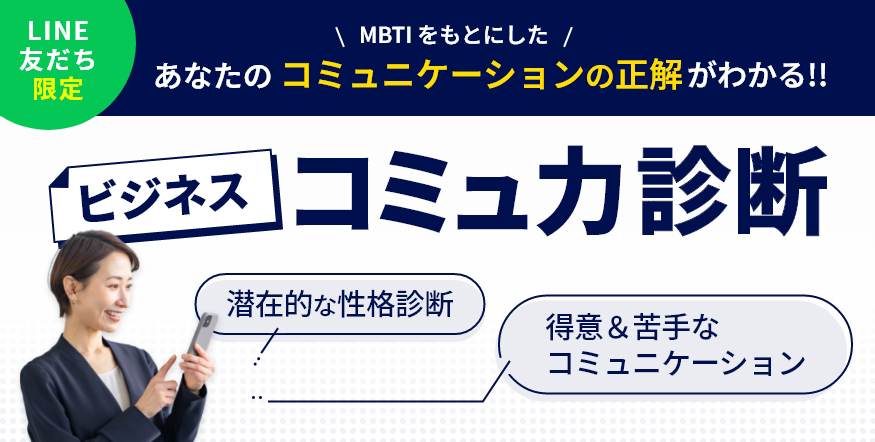






















-420x280.png)






